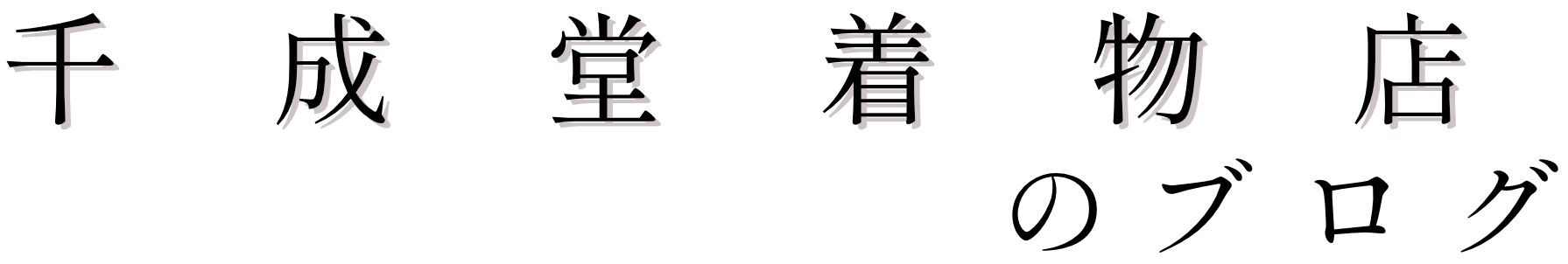単衣の着物を着る時期は?
※ 私は男ですが、基本的に男女とも通じる考え方です。どうかご安心を。
単衣の着物は6月と9月が伝統的な時期ですが、私が考える新たな単衣の時期は「4~5月&9月末~10月」です。
また、状況に応じて11~12月も単衣を着ます。6月は絹上布・7~8月・9月の下旬くらいまで盛夏ものを着るので飛ばします。
当店は神奈川県ですが、4月の平均的な最高気温はだいたい17度。9月は25度。この気温では裏地のある袷着物では汗だくになってしまいます。
また、6月に入ると中旬くらいから絹上布を着ていますので、単衣すらも避けます。
実際問題、スーツ感覚で着物を着る私も一年中単衣で過ごしています。移動は車ですし、室内に基本いますので、袷はむしろ暑くて合理的ではありません。
11月や12月など冬の寒いときは羽織をカーディガン感覚で着て調整しています。
厳格なルールのあるお稽古事以外は、気温優先で単衣を選ぶのは、問題がないと経験上思っています。
どんな着物が単衣に向くか?
基本的にどんな着物でも単衣にすることは可能です。ですが、向き不向きはあります。
大島紬や塩沢、お召し、黄八丈などさらっとした着物は単衣に向きますが、本場結城紬など、縮でない真綿紬の着物は、裾さばきが悪く単衣に向きません。引っかかってめくれます。
また、裏地に染めのない江戸小紋や小紋、無地は、単衣にすると、裏が見えたときに決まりが悪いです。両面染めや裏に染めが通っているものが単衣向きです。
また、ふんわりと厚めの織上がりが好きか、それとも薄めのすっきりした織上がりが好きか・・この辺りは色々試してお好みを見つけてください。
個人的に単衣のおすすめは本場大島紬の良いクラスのものです。シュッとした爽やかな着心地ですが、程よく肉厚感もあり、膝の裏にもしわができにくい。工芸的な着物ならではの味わいもあります。
私は一元式絣の蚊絣を単衣として愛用しています。シンプルですので帯も選びやすいです。

※ 単衣に向かない着物を快適に着るなら、胴裏をつけないで八掛だけをつける「胴抜き仕立て」がおすすめです。この場合の季節は袷になります。
備考欄で希望をいただければ、対応大歓迎です。
単衣におすすめの着尺集
下井紬はさらっとしていて、単衣にもおすすめ。薄手の感触です。

琉球絣ですが、生紬糸で織られたシャリ感のある織上がりはまさに単衣向き。

裏地に染めのきちんと通った着尺なら単衣でお仕立てしても、素敵。

綿と麻の混紡。与那国ドゥタティも単衣におすすめ。
お召や本塩沢などまさに単衣の代表選手。写真は希少な白鷹お召。
単衣の着物に合う帯は?
基本的に袷と同じもので大丈夫です。小物もそうです。
ですが、季節感を意識して、帯を合わせて衿・帯揚げ・帯締めで季節感を出すのがコツです。
例えば、4月・5月の単衣には袷と同じ帯と小物、6月は夏帯や夏小物へ、9月の挽夏にはまた袷小物に戻します。衿から季節を変えたりと小技もありますので、楽しんでください。
紬や洒落ものの場合、大いに感性と気分で選んでよいと思います。ですが、「見るからに暑そう」や「見るからに寒そう」という見た目だけは避けたいところ。
あと、季節柄は少し先取りするのがお洒落です。
単衣が今選ばれている理由・選び方のコツまとめ
昔に比べて気温があきらかに高くなった今です、単衣を選ぶのは正しいと思います。
自由な感覚で着られる洒落ものなら、なおさらです。
織元やメーカー、問屋、着物のスタイリストなど経験豊富なプロでさえ、「単衣がおすすめ」とメッセージを出しています。
また、注目はそのコストパフォーマンスの高さ。冬の時期も含めれば、余裕で半年間をカバーできるのはうれしいところですよね。
「気温優先で着る時期を選ぶ」「大島紬や縮など、さらっと感のある洒落ものが選びやすい」「染ものなら裏にも気を配る」「季節感を小物で出す」
コツをまとめるとこんな感じですが、あなたの着物生活を確かに快適にする単衣。ぜひ挑戦してみてください。また、単衣に向く織物や作品は随時揃えておりますので、お求めの際はお声かけください。
作品担当 井上英樹